| 「白村江」以後 : 国家危機と東アジア外交 (講談社選書メチエ) |
| 森公章/著(講談社)1998/6/10 |
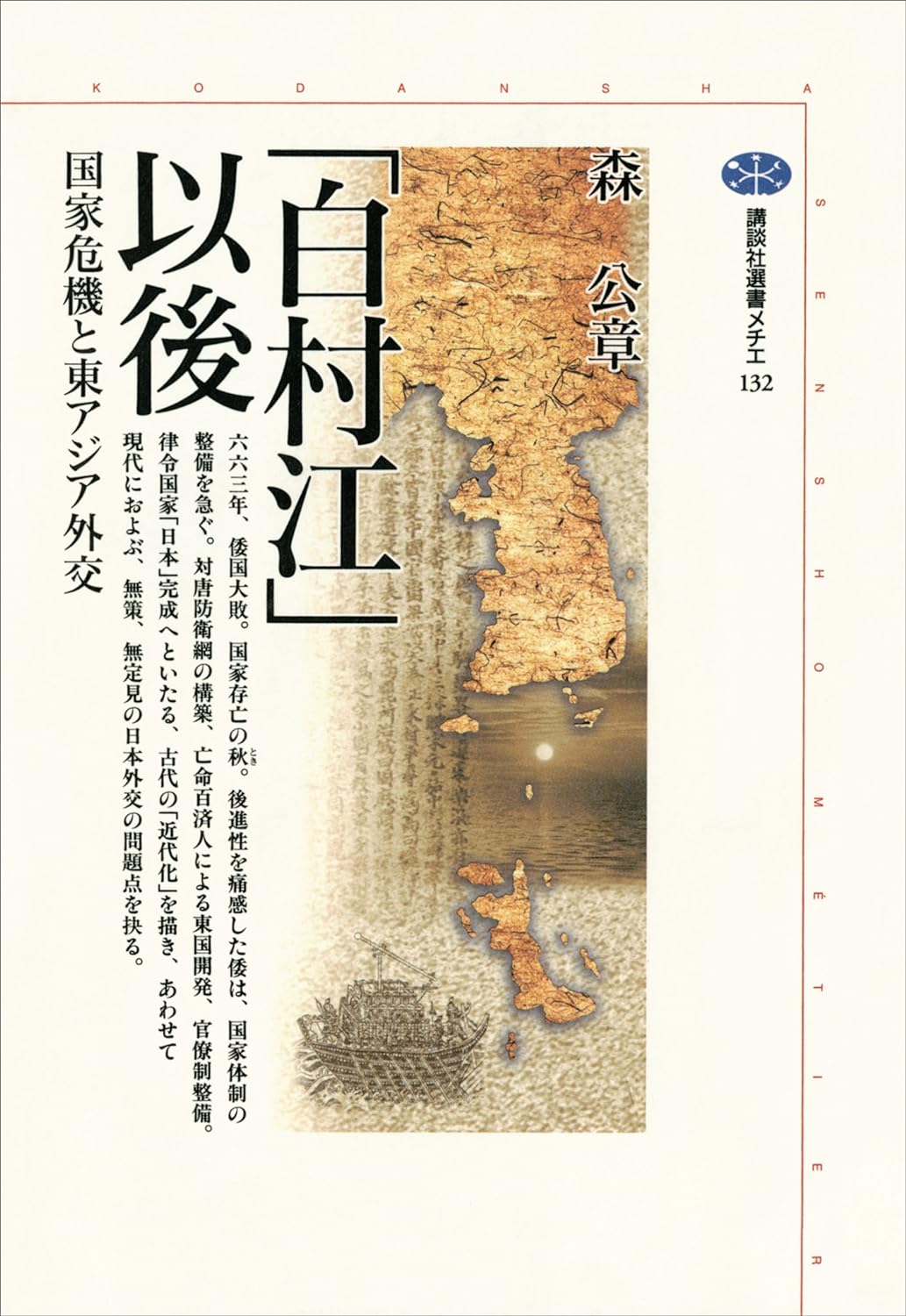
| 2015/8/16 |
| 本書では、白村江の戦を素材に、七世紀後半の東アジアの国際情勢や日本の外交方策について論じ、また白村江の「戦後」の様相にもふれた。白村江への道程として、長年の百済との関係、しかも百済との一国中心主義の外交で、百済を窓口とする文物輸入をおこなっていたため、隋・唐帝国成立以後の東アジアの変動に充分に対処できなかった日本の姿が明らかになった。そうした中での六六〇年、唐・新羅連合軍による百済滅亡である。そして、百済復興運動への肩入れという選択、旧態依然の情勢判断(戦力の構成、戦略構想も含めて)にもとづく戦争の遂行、その結果が六六三年の、白村江での大敗北であった。 この敗戦によって日本は唐と同様の律令国家建設の必要性を実感し、唐文化の全面輸入、律令制度の構築に邁進することになる。隋・唐で完成された律令国家というシステムの導入はみごとに実現し、七〇一年の大宝律令の段附で一応の達成がみられた。一方、白村江の戦以後、朝鮮半島における唐と新羅の戦争、新羅の勝利による唐の勢力の駆逐があり、また唐と対抗する新羅が日本に「朝貢」し、朝鮮諸国に対する日本の「大国」としての体面が保たれたことなどによって、日本の外交方式は変更を迫られずにすんだ。このことが、二つの対唐観の成立や文物の獲得を主とする遣唐使の派遣、また朝鮮諸国に対する主観的外交観の保持を可能にし、外交体質や国際情勢の把握の仕方の面では、変革がおこなわれないままになったと見ることができる。 |
第1章「白村江への道」では、倭の対中国、朝鮮半島外交を扱っています。
著者は、白村江の敗北は、倭の外交面での稚拙さにあると見ています。
607年の遣隋使において、聖徳太子は隋と対等外交を行おうとしたとする説に対し、倭国にはそのような一貫した意図はなく、単に国際的慣行を知らなかっただけだとしています。
そして、倭の外交は一貫して百済一国主義であり、それは乙巳の変前後で変わりはないと見ています。倭は、人・文物の提供の代償として、百済への軍事援助を行っており、倭のこうした行動を傭兵と評する見解もあるということです。
なお、日本書紀に登場する「任那日本府」は、かつての定説では、倭が加耶地域を支配するため設けたもので、百済・新羅に侵食され滅亡したとされていましたが、実際は次のようなものだったと著者は指摘しています(67ページ)。「任那日本府」の「定説」は、後世の創作なのでしょうか。
|
しかし、『日本書紀』を丁寧に読むと、以下のようなことが明らかになってくる。(1)「日本府」は百済・新羅の加耶地域への侵攻が進む六世紀代に登場する。(2)所在地は安羅である。(3)「在安羅諸倭臣」(欽明一五年二月条)がその正式名称である。(4)構成員は倭の中央豪族、吉備臣などの地方豪族、加耶系の人々(倭人との混血児を含む)であり、彼らは五世紀代の倭と半島との関係や地方豪族の独自の通交「例 吉備臣―雄略七年〈四六三〉是歳条)などにより、加耶地域、特に古くから倭とつながりの深かった安羅、有力な渡来系氏族東漢直氏は安羅出身とされる)に居住した倭人の一団であったと考えられる。その中で実務をになっていたのは加耶系の人々であった。(5)倭本国とのつながりはなかったようである。(6)加耶諸国と共通の利害を有し、ほぼ対等な関係で彼らと接し、主に外交交渉は協同で従事している。 特に(5)に関しては、しばしば反百済策をとる「日本府」の官人を「本邑」に返すよう百済聖明王が倭に建言した際、倭は「日本府」に具体的な指示をだすことができなかったこと、また「日本府」は百済におもむいて倭の半島策をたずねており、倭から「日本府」へ直接的に使者を派遣することはなかった事実がわかっている。 |
第2章「百済の役」では、百済滅亡から白村江の戦いまでを扱っています。
660年、唐と新羅の攻撃により百済は滅亡します。唐軍13万は西方海上から、新羅軍5万は東方陸上から侵入し、王都・泗沘(しひ、現在の扶余)、熊津(ゆうしん)が陥落し、義慈王や太子、大臣・将軍ら1万2000人が唐に連行されます。
しかし、すぐに遺民の鬼室福信らが各地で挙兵します。拠点となったのは周留城で、福信は倭国に救援を要請し、質として倭国にいた王子・余豊璋の帰還を乞います。百済滅亡から白村江の戦いまでを日本書紀によって、年表にまとめると次のようになります。内容が一部重複しているのは、日本書紀の記述がそうなっているからです。第1陣は、余豊璋を守って周留城に駐留したものと思われますが、白村江の戦いでは余豊璋は船上にいたようなので、倭軍も同行したのでしょうか。第2陣は新羅国内に進入したものと思われますが、どうような行動をしたのか全く説明はありません。
| 660/7 | 百済は滅亡 |
| 8 | 百済の遺民らが各地で挙兵 |
| 10 | 鬼室福信が百済の王子・余豊璋の帰還を乞う |
| 661/4 | 鬼室福信が百済の王子・余豊璋の帰還を乞う |
| 7 | 斉明大王が筑紫・朝倉宮で急死 |
| 9 | 中大兄皇子が余豊璋に5000の兵(第1陣)を付け百済に送還 |
| 662/5 | 豊璋を百済に送り即位させる |
| 12 | 豊璋が拠点を周留城から避城に移す |
| 663/2 | 拠点を避城から周留城に移す |
| 3 | 倭国が2万7000の兵(第2陣)で新羅攻撃 |
| 6 | 豊璋が福信を殺害 |
| 8 | 倭軍1万余(第3陣)が白村江で大敗 |

白村江の戦いについては、「兵力・装備、作戦、どの面をとっても倭軍には到底勝ち目がなかった」(148ページ)としています。
日本書紀には唐軍170艘、旧唐書には倭軍400艘とされていますが、本書では、倭軍は小舟にすぎず、唐軍は大型船で、蒙衝・楼舡という戦艦も配備されていた可能性もあるとしています。ただ、唐水軍は「熊津江から白江(白村江)に向かい、陸軍と合流して周留城を攻撃するという作戦が立てられた」(144ページ)とあります。熊津江が錦江上流のことだとするならば、戦艦や大型船が航行できたのでしょうか。
また、倭軍が豪族の寄せ集めだったのに対し、唐軍律令制に基づく軍団制度が確立していたことが、作戦に影響したと指摘しています。