| 北条氏と鎌倉幕府(講談社選書メチエ) |
| 細川重男/著(講談社)2011/3/10 |
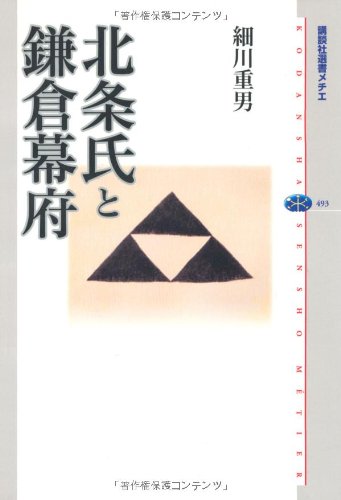
| 2015/9/6 |
その「論理」とは、次のようなものです(220ページ)。
|
①鎌倉将軍は、武家政権創始者源頼朝の後継者である。 ②北条氏得宗は、八幡神の加護を受けし武内宿禰の再誕北条義時の後継者である。 ③義時の後継者である北条氏得宗は、鎌倉将軍の「御後見」として鎌倉幕府と天下を支配する。 |
①については、源氏将軍は、頼朝、頼家、実朝の三代で途絶え、後は頼朝の姉の血筋を継ぐ摂家将軍二代、その後は源氏の血筋とは無縁な親王将軍が四代続いています。ここに至っては、もはや「源頼朝の後継者」とは言えない感じもしますが、著者はこの点について、次のように説明しています(195~196ページ)。
|
鎌倉後期から南北朝初期の将軍にとって、必要であったのは、清和源氏であることではなく、頼朝の後継者であることではなかったろうか。「右幕下」「右大将家」(共に頼朝が任官した右近衛大将のこと)、あるいは「二品」(ここでは二位のこと。正二位か極位だった頼朝を指す)として神格化した頼朝の後継者であることが、武家政権の首長たる将軍にとって必要な資格であったのではないか。鎌倉末期成立の幕府訴訟解説書『沙汰未練書』は「将軍家トハ、右大将家(源頼朝)以来代々関東政務之君御事也」「地頭トハ、右大将家以来、代々将軍家奉公、蒙御恩人之事也」と記しているのである。 「鎌倉将軍は頼朝の後継者である」という観念を具現化した者こそ、七代将軍源惟康であった。前述のごとく、文永七年(一二七〇)、時宗二十歳の十二月、惟康は七歳で源氏賜姓を受け、源実朝横死以来五十一年ぶりで鎌倉に源氏将軍が復活した。時宗二十九歳の弘安二年(一二七九)正月、惟康は十六歳で正二位に叙す。五年後の同七年四月、時宗は三十四歳で没するが、惟康は同十年六月五日、二十四歳で右近衛大将に任官するのである。 つまり、惟康は時宗政権下で源氏・正二位となり、時宗没の三年後に右近衛大将となったのである。源氏・正二位・右近衛大将は、すべて頼朝に通じる。惟康は頼朝の再来であった。 |
②は、北条義時は武内宿禰の生まれ変わりだという伝説です。
著者によると、この話は「古今著聞集(ここんちょもんじゅう)」(1254年)と「平政連諫草(たいらのまさつらかんそう)」(1308年)で触れられており、「鎌倉末期にはこの伝説が鎌倉幕府中枢を含めた武家社会知識層の間に広く知られていたことを示している」(85ページ)とのことです。
北条義時と武内宿禰を比較すると次のようになります。著者は、ⅱ、ⅲ、ⅳの類似を指摘し、さらに、ⅴ「ともに追討命令を蒙るも助かった」ことに王朝貴族が飛びついたと推測しています。天皇の追討宣旨を蒙りながら、それに反抗し勝利するということは、まさにあってはならない驚天動地の事態であり、「追討命令を蒙るも助かった」先例を武内宿禰に見出し、北条義時は武内宿禰の生まれ変わりだという伝説につながったというものです。そして、北条政権を正当化する根拠として、その伝説が鎌倉武家社会に受け入れられたとするのです。
| 武内宿禰 | 北条義時 | |
| ⅰ | 300歳超 | 61歳(1163-1224) |
| ⅱ | 5代の天皇に仕える | 4代の将軍に仕える |
| ⅲ | 神功皇后を助け香坂・忍熊両王の乱を平定 | 政子を助け承久の乱を平定 |
| ⅳ | 応神天皇の後見 | 4代将軍・藤原頼経の後見 |
| ⅴ | 追討命令が出るが無実を証明し勅免 | 追討宣旨が出るが承久の乱に勝利 |
③については、「得宗」は北条義時に関係する何かであるとされているそうですが、「得宗が義時と結びつく語であることを示す史料は、実は極めて少な」
く、「実はよくわからない」と著者は述べています(90ページ)。
著者は「佐野本北条系図」によれば、浄土系信者であった義時の法名は「観海」であった可能性が高いとし、「得宗」が本来の義時の法名であったとする説を否定しています(92ページ)。
そして、「得宗」は「徳崇」の当て字、略字であり、「徳崇」は時頼が曽祖父義時に贈った禅宗系の追号であったと推測しています。庶子であり北条家家督としての正統性を欠く時頼が、同じく庶子でありながら家督を継承した義時に「徳崇」の追号を贈り、自らの法名に「道崇」を選び共通性を誇示したというのです(95ページ)。
かくして、著者の言う「北条氏の鎌倉幕府支配を支えた論理」が完成するわけですが、推論に推論を重ねているという感じがしないでもありません。
著者は、鎌倉武士の知的レベルについて次のように述べています(10ページ)。
|
鎌倉武士・鎌倉御家人とは、こんな連中なのであり、こんなヤツらが鎌倉幕府を作っていたのである。平安・鎌倉時代の武士たちは、自分たちを「勇士」と称し、他者からも、そう呼ばれていたが、その「武勇」とは、こういうことなのである。ようするに野蛮人なのだ。王朝貴族は東国武士を蔑んで「東夷」(東に住む野蛮人)と呼んだが、まったくそのとおりである。 王朝は奈良時代以来、全国を覆う律令制の支配機構を持ち、その支配機構の歴史は鎌倉幕府が成立した十二世紀末には、ほとんど五百年に及ばんとしていた。この間、王朝貴族は外交を含めた政権運営のデータとノウーハウを積み垂ねていた。しかし、紛争解決の方法として相手を殺すことを即座に選ぶ武士たちが作った鎌倉幕府は、まさに蛮族の政権であり、王朝のような知識の蓄積は、ほとんどなかっか。鎌倉武士たちは、支配機構を手探りで作っていったのである。 |
|
『増鏡』は、時宗は「お二つの皇統で皇位におつきになるようにしよう(御二流れにて、位 |