| 南京事件「虐殺」の構造増補版(中公新書) |
| 秦郁彦/著(中央公論新社)2007/7 |
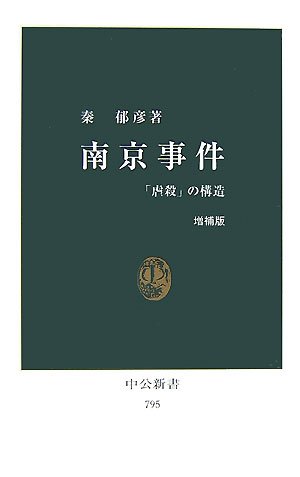
| 2012/3/17 |
そこで、南京事件のことを調べてみようと、アマゾン検索で始めに表示される「南京事件 (岩波新書)」をまず読んでみましたが、続いて検索で2番目に表示される本書を読んでみました。
秦郁彦氏といえば、正論や諸君にしばしば登場する保守派の現代史家というイメージがあって、本書も南京大虐殺を否定する論調で貫かれているのかなと思っていましたが、「第5章 検証――南京で何が起きたのか(上)」「第6章 検証――南京で何が起きたのか(下)」では、日本軍の記録文書や兵士の日記などから、大量殺人の実態を検証しています。さらに、事件の背景に関する事実は、「南京事件 (岩波新書)」で述べられているものとほぼ共通しています。どうも予想とは異なるようです。
さらに、初版あとがき(本書は、1986年に発行された初版に、第9章と第10章の南京事件論争史を追加した増補版です。)に、次のような記述があります(244ページ)。
| 日本が満州事変いらい十数年にわたって中国を侵略し、南京事件をふくめ中国国民に多大の苦痛と損害を与えたのは、厳たる歴史的事実である。それにもかかわらず、中国は第二次大戦終結後、百万を越える敗戦の日本兵と在留邦人にあえて報復せず、故国への引きあげを許した。昭和四十七年の日中国交回復に際し、日本側が予期していた賠償も要求しなかった。当時を知る日本人なら、この二つの負い目を決して忘れていないはずである。 それを失念してか、第一次史料を改竄してまで、「南京"大虐殺"はなかった」といい張り、中国政府が堅持する「三十万人」や「四十万人」という象徴的数字をあげつらう心ない人々がいる。もしアメリカの反日団体が日本の教科書に出ている原爆の死者数(実数は今でも不明確だが)が「多すぎる」とか、「まぼろし」だとキャンペーソを始めたら、被害者はどう感じるだろうか。 数字の幅に諸論があるとはいえ、南京で日本軍による大量の「虐殺」と各種の非行事件が起きたことは動かせぬ事実であり、筆者も同じ日本人の一人として、中国国民に心からお詫びしたい。そして、この認識なしに、今後の日中友好はありえない、と確信する。 |
| いわゆる「まぼろし派」と「大虐殺派」の論争を見ても、定義がはっきりしていないため、論点はさっぱりかみ合っていないように思える。洞富雄氏が「まぼろし化」と命名するきっかけを作った鈴木明『「南京大虐殺」のまぼろし』(文藝春秋昭和四十八年)を読んでみると、鈴木氏が明確に「まぼろし」と断じているのは「百人斬り」伝説ぐらいで、全面的に日本軍の非行を否認しているわけではなく、一般的には肯定していることが判る。 つまり書名と内容が食いちがっているのであり、書名を『南京大虐殺にはまぼろしの部分もあった』とでもしておけば、誤解は避けられたかも知れない。丈句なしの力作であるだけに惜しまれるところだ。 中国から「人だましの本」(『世界知識』一九八五年八月七日号)と批評された田中正明『"南京虐殺"の虚構』(日本教文社昭和五十九年)も、同じく「羊頭狗肉」に近い。書名と、「本書を読んで、今後も南京大虐殺を言い続ける人がいたら、それは単なる反日のアジをやっている左翼と烙印を押してよいだろう」と言い切る渡部昇一氏の推薦文を見たそそっかしい読者は、やはり全部が「まぼろし」の空中楼閣だったのか、と早合点するだろう。 |
| どうやら「まぼろし」とはゼロではなく、数千人の幅までふくむ概念らしいと推測されてくるが、「大虐殺」の概念の方もやはり問題がありそうだ。呼称の由来を当ってみると、事件を最初に報道した英人記者のティンパーリーは”Japanese
Terror”(訳語は「日本軍の暴行」)と表現しているが、一般的には「南京アトローシティ」が使われたらしい。 日記に基づいて書かれた当時の外務省東亜局長石射猪太郎の回想録に、「私は当時から南京アトロシティーズと呼んでいた……」(『外交官の一生』三〇六ぺージ)とあるのが有力な裏付けになる。 しかし英和辞典を調べてみると、「アトローシティ」(atrocity)という英語は広く残虐行為を意味し、虐殺と同義ではない。虐殺にはmassacreという、より適切な英語があり、西洋史では「セント・バーソロミューの虐殺」や、アメリカ独立戦争の発端となった「ボストンの虐殺」(Boston Massacre)が著名だが、後者で殺されたのはわずか数名である。第二次大戦では数百万人のユダヤ人をガス室に送った「アウシュビヅツの虐殺」や数千人のポーランド人青年将校を集団殺害した「カチソの森の虐殺」が知られている。 してみると、"虐殺"は、殺された人数の多少よりも、事件全体の性格、とくに組織性・計画性に関わる概念らしいと見当がつく。現在でも欧米ではアトローシティかレープを使うのが一般的で、ディック・ウィルソンの近著『虎が戦う時』(When Tigers fight)にはRape of Nanking。レープは法律用語としては「強姦」だが、広義では各種の「暴行」を意味する。 ついでに書くと、中国側では「(大)屠殺」と呼んでいる例が多いようだが、これも"虐殺"にふくまれる組織性・計画性のニュアンスは稀薄である。 わが国の「大虐殺派」は「西のアウシュビヅツ、東の南京」と好んで並べるが、この二つは本質的に別物と考えるべきだろう。 |
さらに、秦氏は「大虐殺派は中国の誇大な言い分をそのまま受け入れている」と反発しているようで、次のように述べています(205ページ)。
| この観点に立って、各種の数字を比較すると、中国の初級中学用教科書が採用し、一九八五年八月江東門にオープンした南京大虐殺記念館がかかげている「一般市民三十万以上」(帝国書院版『世界の歴史教科書』シリーズ(22))、南京大学歴史系編著「日本帝国主義の南京における大虐殺」(一九七九年、内部刊行物)の「同胞四十万人前後」は、往年の大本営発表のようなものと考えてよかろう。大本営発表は戦果が誇大すぎて悪評紛々だが、必ずしも全部がデッチあげだったわけではない。…… ……「米航空母艦十一隻撃沈」と発表して、お祝いの日本酒まで特配したのに、あとで戦果ゼロと判った台湾沖航空戦の場合も、関係者によると、攻撃に参加した航空隊から上ってくる報告を足し合わせたもので、怪しいとは思ったが、カットする根拠もないので、そのまま発表したものだという。ましてや人口統計もしっかりしていないうえ、「白髪三千丈」の伝統を持つ中国のことだ。悪意はなくても、数字がふくれあがるのはやむをえまい。 |
| ……宮沢談話と「近隣諸国条項」は一人歩きして、翌年からの教科書検定は大幅に緩和され、なかでも南京事件に関する記述はフリーパスも同然となってしまう。 すなわち一九七五年以前は、南京事件を取りあげた教科書は家永教科書をふくめ、小中高を通じ皆無だったのが、七五年から中学、高校各一社、八〇年検定では中学が五社、高校が一社と漸増しつつあった。しかし記述スタイルは「戦線外で平服で銃撃する者(便衣兵を指す)があったので、占領の混乱時に、日本兵は女・子どもをふくむ多数の住民を殺した」(日本書籍・中学校用)が代表するように、脚注の部分で扱ったり、人数は「多数」とぼかしたり、「混乱のなかで」とか便衣兵の役割に言及するなど、かなり抑制した書き方になっていた。 だが八三年度検定から、トーンはがらりと変る。まず南京事件を取りあげた教科書が中学では七社全部、高校は五社のうちの四社と激増した。記述は詳しくなり、一〇万、二〇万、三〇万以上といった被害者数を記す教科書がふえた。 採択では、文部省の検定より影響力が強いと言われた日教組の八四年版白書が「アウシュビッツ=ナンキン=ヒロシマ」と位置づけ、南京を書くのは「絶対条件」と注文したこともあってか、南京についての記述は全般に過激、偏向の度を加えていった。 |