| 日清戦争:近代日本初の対外戦争の実像(中公新書) |
| 大谷正/著(中央公論新社)2014/6/25 |
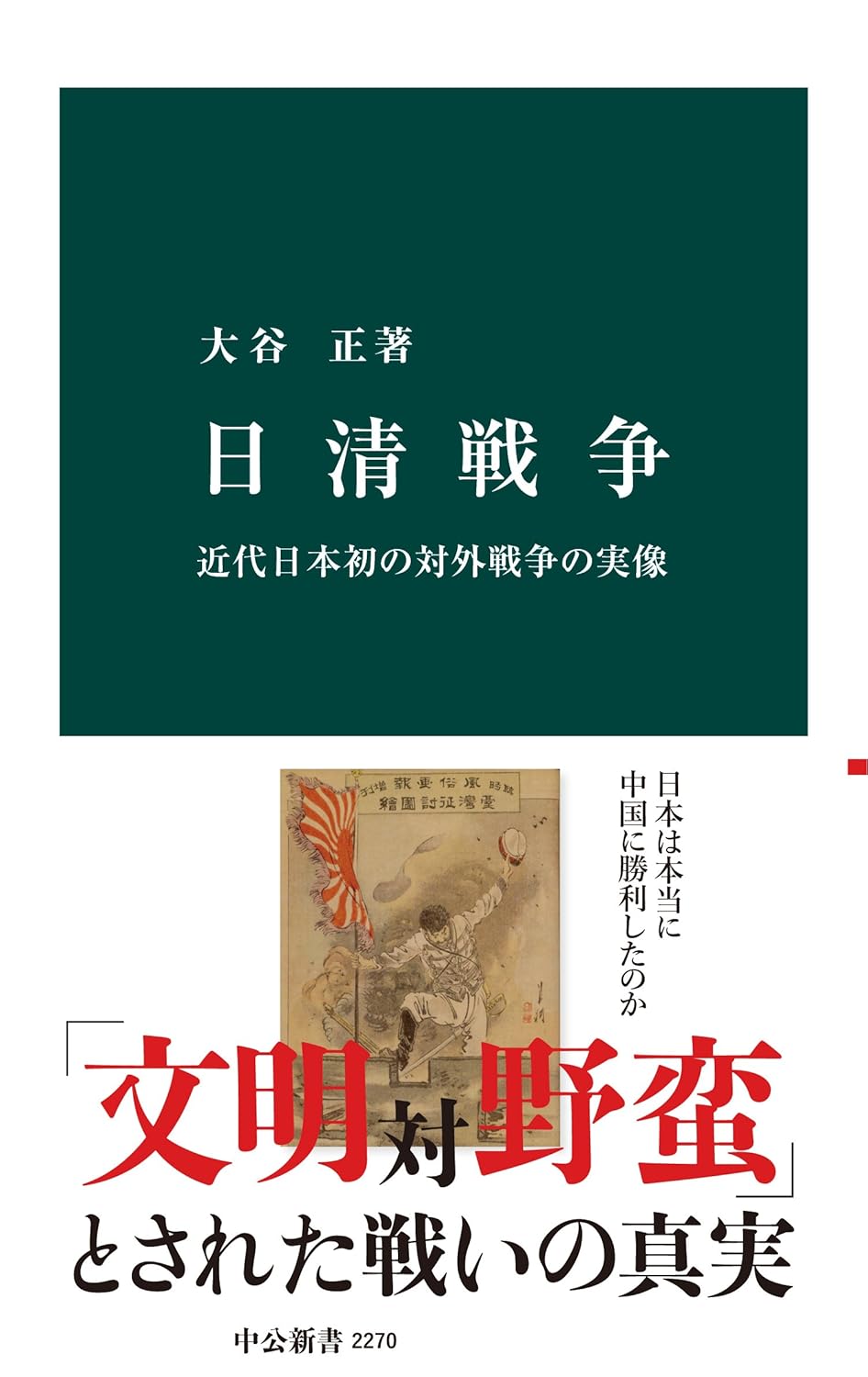
| 2020/8/17 |
| 第1章 戦争前夜の東アジア 第2章 朝鮮への出兵から日清開戦へ 第3章 朝鮮半島の占領 第4章 中国領土内への侵攻 第5章 戦争体験と「国民」の形成 第6章 下関講和条約と台湾侵攻 終章 日清戦争とは何だったのか |
日清戦争は防衛戦争?
高校講座日本史>日清戦争は次のように述べ、日清戦争は防衛戦争であったことを示唆しています。
| 19世紀後半、日本政府は、「列強(れっきょう)」の東アジア進出に強い危機感を抱きました。 なかでも、朝鮮をめぐって恐れたのがロシアの勢力拡大です。 朝鮮がロシアの勢力下に入ると、日本は自国の独立も危うくなるのではないかと脅威を感じたのです。 政府は先に主導権をとり、朝鮮を独立させ、日本の影響下に置くことで、ロシアなど列強と対抗しようと考えました。 しかし当時、朝鮮を属国(ぞっこく)とみなしていた清が、政治や外交の権限・宗主(そうしゅ)権を有すると主張。 これを否定した日本は、清との対立を深めていきます。 |
| 1894年、朝鮮の南部で、大規模な農民の蜂起(ほうき)が起きました。 「甲午(こうご)農民戦争」です。 減税と外国人の排斥(はいせき)を訴える農民の武装蜂起でした。 この鎮圧のため、朝鮮政府は清に援軍の派遣を要請します。 清が出兵すると日本もこれに対抗し、朝鮮に出兵しました。 両国の出兵で農民の蜂起はおさまりました。 しかし、朝鮮政府の内政改革をめぐって日清両国は対立を深め、交戦状態となります。 |
なぜ無理を重ねて開戦に踏み切ったのか
著者は、本書の目的を次のように説明しています(ⅲ~ⅳページ)。
つまり、①李鴻章は戦争回避に努力したにもかかわらず、日本は、なぜ無理を重ねて開戦に踏み切ったのか、②なぜ満州・山東半島・台湾・澎湖諸島にまで拡大した全面戦争となったのか、③そもそも戦争は不可避だったのか、といった疑問を解き明かすのが本書の狙いであると思われます。
| 日清戦争の場合、朝鮮問題を契機に戦争を仕掛けたのは日本側で、清とりわけ北洋通商大臣(以下、北洋大臣と略称する)として清の対朝鮮外交の責任者であった李鴻章は戦争回避に努力した。さらに東アジアに権益を持つ欧米列強、特にイギリスとロシアは戦争回避のために調停に乗り出した。にもかかわらず、なぜ日本側が無理を重ねて開戦に踏み切ったのか、なぜ開戦後の戦争が朝鮮を舞台とした地域的・限定的な戦闘にとどまらず、満州・山東半島・台湾・澎湖諸島にまで拡大した全面戦争となったのかについては、議論する人によって意見が異なった。 かつては、日本が西欧的な近代化政策を進めるためには、清を中心とする東アジア国際秩序の再編成は不可欠であり、明治維新以後の日本による朝鮮・中国侵略政策の延長線上に日清戦争は避けられなかったという見方が有力であった。つまり日本の政府も軍も、日清間の戦争を不可避と考え、準備を重ね、開戦にいたったという考え方で、現在でもこのような考え方が通説として流布している。しかし、一九八〇年代以降、研究者の間では、このような日清戦争必然説は実証的に批判されるようになった。 日清開戦に関する研究だけでなく、日清戦争の軍事史研究や社会史研究か深まったのも、近年の研究の特徴である。さらに東アジア国際関係史の新たな研究が発表され、また日本軍占領下の朝鮮における第二次農民戦争や台湾の抗日闘争にも目が向けられるようになった。このような多方面の研究の進展によって、比較的小さな戦争であるにもかかわらず、規模の大きい日露戦争よりも複雑な様相を示す戦争であり、戦争の結果が日本と東アジア世界に大きな変化をもたらした日清戦争を、東アジア地域史のなかに位置づけて、さまざまな側面から立体的に理解する条件か整ってきた。 本書は、以上のような近年の日清戦争研究の水準をわかりやすく読者に提示することを目的とし、次のような内容で筆を進めることとしたい。 |
征韓論争はどうなったのか
「第1章 戦争前夜の東アジア」では、日清戦争に至る19世紀後半の情勢を扱っています。
1863年、李氏朝鮮国王・哲宗が死去、跡継ぎがいなかったため傍流の高宗が12歳で即位し、実父の大院君が、金氏(外戚)の勢力を排除し実権を握ります。しかし、1873年、高宗が成人すると大院君を引退させ親政を始めます。そして、王妃閔妃の一族が取り立てられ、次第に実権を握るようになります。高宗を挟んで大院君と閔妃が熾烈な権力闘争を繰り広げ、結局、大院君は敗北します。しかし、日本勢力が介入し、閔妃を殺害し、高宗から王位(帝位)を奪い、2010年の韓国併合で国家は消滅します。なお、閔妃は、韓国や中国では、明成皇后という呼び方が浸透しているそうです(知っていますか明成(ミョンソン)皇后)。
本書の記述を参考に、この間の経緯を年表にまとめてみました。明治六年政変では征韓論を主張した西郷が政争に敗れて下野したとされていますが、内治優先を主張した大久保は着々と朝鮮進出への布石を打っています。
| 1864 | 李氏朝鮮国王死去、傍流の高宗が即位。実父の大院君が、金氏(外戚)の勢道政治を廃し、実権を握る |
| 1873 | 明治六年政変、(征韓論争に破れ?)西郷が下野 大院君が引退、高宗が親政開始。王妃閔妃の一族が実権を握る。 |
| 1875 | 江華島事件(内治優先のはずの明治政府が積極介入) |
| 1876 | 日朝修好条規で欧米諸国の先陣を切って朝鮮に開国させる |
| 1877 | 西南戦争(征韓論争はどうなった?) |
| 1879 | 琉球処分、朝貢国消滅に清が危機感 |
| 1881 | ロシアへの危機感高め、朝鮮政府が開化政策開始、行政機構の近代化、日本人武官を招き西洋式軍隊の別技軍創設 大院君は、閔氏政権を倒し李載先を国王に即けようとするが失敗 |
| 1882 | 米朝修好通商条約調印 壬午軍乱(開港で米価高騰の不満、閔妃と日本への恨み爆発) |
| 1884 | 甲申事変(清に接近する閔氏政権に対する親日派クーデター) |
| 1885 | 天津条約で日清の協調体制が成立 |
本書では全く触れられていませんが、江戸時代の日朝間には、釜山の草梁倭館を通じて、外交通商関係がありました(江戸時代の日朝交流と倭館跡)。ところが、明治政府になって両国の外交関係に緊張が高まります。明治政府は、王政復古により復権した天皇が朝鮮国王より名分論的に上位にあると主張したのに対し、朝鮮は旧例に反するという理由で国書の受理を拒絶したからです。そこで、「武力でもって物の道理を朝鮮に悟らせよう」という征韓論が登場します(ジャパンナレッジ征韓論参照)。ただし、征韓そのものは維新政府の指導者に共通した構想だったようです(日本人の朝鮮観 その光と影)。
朝鮮の改革を諦め、脱亜入欧路線に転換
閔氏政権はその後、日本に接近し、日本人武官を招き西洋式軍隊の別技軍創設します。一方、開港で米価高騰し、不満を持った下級兵士や下層民は、1882年、暴動を起こし、別技軍、日本人武官、日本公使館、閔氏政権高官を襲います(壬午軍乱)。
大院君は反乱軍に担がれたものの計画に直接関与はしていなかったようです。しかし、清は大院君を事件の実質的責任者と見なして、天津に連行し、閔氏政権は復権します。
金玉均ら急進開化派は、1884年、清の影響力の排除を目的に、閔氏政権に対してクーデター(甲申事変)を起こしますが失敗し、金玉均らは日本に亡命します。「このクーデター計画には日本政府と福沢諭吉らの民間人が関わっていたことが様々な史料から明らかになっている」という意見もあります(世界史用語解説 授業と学習のヒント>甲申政変/甲申事変 )。
世界史講義録/朝鮮の開国と日清両国の動きでは、金玉均と日本・福沢諭吉らとの関係と甲申事変の流れを「金玉均は1882年にも日本に視察旅行をし、朝鮮の改革に期待を寄せる福沢諭吉の紹介で井上馨、大隈重信、渋沢栄一などと面識を得ており、今回も福沢などと接触して、日本をモデルにして一刻も早く朝鮮の近代化を図ることが必要と考えるようになりました。帰国後、金玉均らは急進開化派として政治改革を試みますが、守旧派の抵抗で身動きがとれず焦りを募らせていました」「1884年12月4日、金玉均ら急進開化派は、クーデタを決行しました。ソウル駐在日本公使が軍事援助を約束したのです。また清の朝鮮駐屯軍が清仏戦争の影響で3000名から 1500名に減らされたことも好機と考えられました」「金玉均らは、国王の身柄を確保した上で閔妃派の政府要人を殺害し、5日には新政権樹立と改革を宣言しました。この間日本兵約150人は王宮の占拠にあたっていました。しかし、6日に袁世凱率いる1500名の清軍が王宮に至り日本軍を攻撃すると、日本軍は小競り合いの後に金玉均ら開化派を見捨てて退去しました。また事件を知った民衆によって日本公使館が焼き討ちにあい日本公使もソウルから逃れました。閔妃派の守旧派政権が復活し、事件に関わった開化派は処刑され金玉均は日本に亡命しました。この事件を甲申政変といいます」と述べています。ここでは、事件と福沢諭吉の直接の関係には言及していません。
2つの事件を比較すると、次のようになります。壬午軍乱では、日本に接近した閔氏政権が標的とされましたが、甲申事変では、清に乗り換えたことにより閔氏政権が標的とされました。福沢諭吉は朝鮮の改革を諦め、脱亜入欧路線に転換します。
| 壬午軍乱(1882) | 甲申事変(1884) | |
| 主体 | 下級兵士、下層大衆(大院君) | 金玉均ら急進開化派、竹添公使、日本兵 |
| 標的 | 閔妃・閔氏政権高官、日本公使館、別技軍 | 閔氏政権 |
| 目的 | 開化政策の撤回 | 清の影響力の排除 |
| 結果 | 清が軍隊派遣し軍乱を鎮圧、大院君を連行、閔氏政権が復活 | 清が出兵、日本兵は退去、急進開化派は亡命、処刑 |
勢いを増す主戦論
甲申事変において、日本が出兵を計画していたとするならば、本格的な軍事衝突になる可能性もあったことになります。
本書によると、このころ日本政府内には、伊藤博文ら和平派・長州派と強硬派・薩派の対立があったが、「薩派はまとまりに乏しく、政治力では長州派に後れを取っていた」(15ページ)ということです。しかし、甲申事変後は主戦派が勢いを増し、次のように(15~16ページ)、事件後の交渉は伊藤博文の藩閥政府に厳しいものになると予測されていました。
| しかし、竹添公使の稚拙な内政干渉の結果として生じた甲申政変とその失敗は、朝鮮政策を担ってきた井上・伊藤らの長州派の大失策であり、薩派の発言力が高まっていた。さらに対朝鮮・対清強硬論が支配的な世論と対清開戦熱を煽った民間の好戦的ジャーナリズムは、薩派・主戦論者の背中を押した。 その結果、清との交渉に臨むために決められた政府の対清要求項目は、朝鮮からの日清両軍の撤退など、清の拒否が予想される強硬なものとなり、さらに清が日清両国軍の撤退を拒否したときは、戦争を行うことが決まる。 甲申政変の結果、清の軍隊が勝って日本の勢力か駆逐されている状態で、負けた側の日本が日清両国軍の同時撤退を主張するのは無理があり、交渉決裂の可能性は高かった。薩派が対清交渉を開戦への道筋と位置づけているなかで、井上外務卿と対清交渉を担った藩閥政府トップの伊藤博文は厳しい立場に立たされる。 |
| 三月一四日、特使として天津に到着した伊藤博文は厳しい交渉を予想していたが、平和解決を望むイギリスが事前に清を説得したこともあり、李鴻章との交渉で両国の撤兵への合意が実現する。宗属関係に関わる朝鮮への再派兵問題については対立が続いたが、最終的には両国がたがいに朝鮮への再派兵権を認め合い、軍隊を撤兵させることで妥協が成立、一八八五年四月、これらの内容を記した天津条約が成立した。戦争は回避され、日本国内では長州派の政局主導が維持された。 |
ロシア脅威論は根拠薄弱
このころ、英国がロシア極東艦隊の日本海への回航阻止のため朝鮮南部の巨文島を占領し砲台を築いたことから、ロシアが南下するのではないかというロシア脅威論が起こり、日本政府ではその対抗策として清との協調政策を取ることとなります。
このロシア脅威論について、著者は次のように述べて(17~19ページ)、根拠薄弱であったと指摘しています。
| 井上外務卿はロシア脅威論を強調することによって、朝鮮問題に対する日清英の協調体制の構築を提起したか、ロシアの脅威は本当に存在したのだろうか。この問題について考える場合、ロシア側の意図と能力の両面から考える必要があるが、結論的に言えば一八八五年段階でロシアが朝鮮を獲得する意図と能力を持っていたとは考えにくい。 一八八八年五月八日、ロシア皇帝の命令を受け、プリアムール総督(バイカル湖以東の極東ロシア領全体を管轄する役職)の侍従武官長コルフ男爵とロシア外務省アジア局長ジノヴィエフの朝鮮問題に関する特別会議が行われた。その結論は「朝鮮の獲得は我々に如何なる利益も約束せぬばかりか、必ずや極めて不利な結果をもたらすであろう」という判断であった。 その判断の根拠として、①朝鮮獲得による経済的利益は、将来はともかく、現段階ではわずかである。②朝鮮を獲得すれば重要な戦略的基地となる可能性はあるものの、その防衛はプリアムール軍管区の限られた軍事能力では重荷でありすぎる。③朝鮮獲得は日本・清・イギリスとの関係を損なう。この三つの理由があげられている。そのうえで、ロシア側のとるべき対応として、甲申政変の失敗で朝鮮への介入を控えている日本政府と協調し、朝鮮の現状維持を図ることに努めるべきだと結論づけていた。 この一八八八年の特別会議は、朝鮮問題に関するロシア政府の国家意思を確定したものである。ロシア政府の意図は、朝鮮の現状維持を第一の優先課題とし、その課題を日本をはじめとする関係諸国との協調を基礎として実現しようとするもめであった。一八八八年の資料を分析することで一八八五年のロシア政府の意図を推定することには一抹の不安があるが、この他の関連資料を見ても、やはり八五年段階の井上外務卿を筆頭とする日本政府内のロシア脅威論は根拠薄弱で、日本側の思い過ごしであった。 |
壬午軍乱当時の日本の軍事力は清に比べ弱体だったと次のように述べています(24~25ページ)。
| 日本では一八七三年の徴兵令公布とともに徴兵制による近代軍が誕生する。国内治安維持を主な目的として発足したが、一八八〇年代の軍拡によって、日清戦争直前には対外戦争に対応できる軍隊に成長していた。 一八七七年の西南戦争が終わって以後、松方正義大蔵卿の行った緊縮財政(松方財政)の下で日本の陸海軍は小規模なままで、日本の軍事力は壬午軍乱の発生した一八八二年段階では、軍事力の近代化を先行させていた清に比べると弱体だった。 壬午軍乱の際、陸軍の常備兵数は一万八六〇〇余に過ぎず、予備役兵二万七六〇〇余を合計しても四万五〇〇〇名ほどであった。兵力不足を補うため、西南戦争と同じように警視庁巡査の動員が検討されたか、淮軍だけでも一〇万を超える兵力を有する清と戦うのは困難だった。海軍は二四隻、二万七〇〇〇トンで、小型艦と旧式艦を含み戦力は低かった。 このとき、対清開戦を主張する強硬派が存在したことはすでに述べたが、冷静に考えるとこの兵力で正攻法で清と戦って勝てると考えた軍人は当時も少なかった。 |